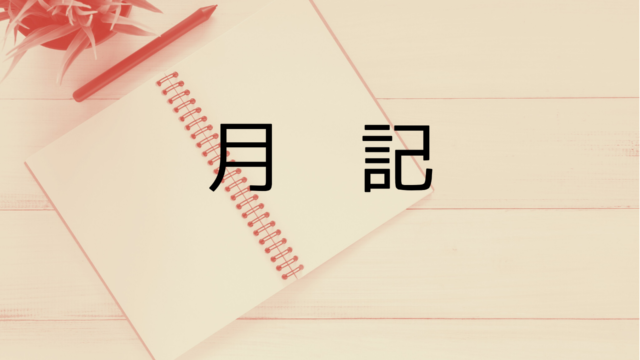施工計画書とは
施工計画書については標準仕様書(電気設備工事編)の中で次のように定められています。
第1編 第2節 工事関係図書
1.2.2 施工計画書
(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整の上、十分検討する。
(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。
「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(平成31年度)より抜粋
施工計画書は、工事の着手から完成までの現場での約束事を受注者が自ら具体的に検討し作成するものであり、その内容は主に、現場の施工体制、仮設計画、安全・環境対策、工程計画、品質計画などで構成されます。
作成するのは上記(1)(3)より次の2種類となります。
・総合施工計画書(以下「総合」)
・工種別施工計画書(以下「工種別」)
施工計画書の提出時期
施工計画書については、発注者によって具体的な記載例や作成の手引きが公開されている場合もありますので、作成の際の参考にすることができますが、それらを踏まえながら作成時の注意点やポイントをいくつかご紹介したいと思います。
今回は、「施工計画書の提出時期について」です。
総合、工種別の提出時期については標準仕様書の中で、それぞれ「工事の着手に先立ち」、「工事の施工に先立ち」と定められています。
工種別の提出時期については、その施工前とされていますが、現場では「施工が進んでいるのに工種別施工計画書が提出されていない」という問題がしばしば起きることがあります。計画書は原則すべての工種が対象となりますが、小規模工事で作成を省略できる工種がある場合などは発注者の承諾が必要となるため、あらかじめ総合の中で作成する工種とその提出時期について記載しておくとこうした問題を回避できるかと思います。
「工事の着手」とは
一方、総合の「工事の着手」がいつの時点を指すのか。
これについてはいくつかの時点が考えられますが、標準仕様書には具体的に示されていません。
たとえば、設計図書の照査のために行う現地確認は標準仕様書でいう「着手」に当たるのでしょうか。
もちろん異なる見解はあると思いますが、設計図書の照査のための現地確認や、仮設計画のための現地確認、電力会社等の関係機関との事前協議などは「着手」には当たらないと考えられます。(というより、仮設計画のための現地確認などは施工計画書の作成に必要なことですので、これを「着手」と捉えるのは矛盾を生じることになってしまうでしょう)
ではどの時点を「着手」とするのか、「電気通信設備共通仕様書」(国土交通省)の中では次のように定義されています。
第1編 第1章 第1節 1-1-2 用語の定義
42. 工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。「電気通信設備工事共通仕様書」(令和元年6月)より抜粋
営繕工事では詳細設計を含む発注というのはほとんど見かけませんので、現場事務所の設置や起工測量などが着手の目安と考えられるのではないでしょうか。しかし、そうなると測量を伴う照査は着手に当たることになりますので、照査に関する作業であっても着手に当たるか当たらないかはその内容によって慎重に判断する必要がありそうです。
具体的には、
既存設備や機器配置確認など発注図と現場を照合するための現地確認は許容範囲といえますが、測量作業や高所、受変電設備内などで事故につながるおそれのある作業を行う場合は、施工計画書の提出後に行うべきでしょう。
(参考)
山梨県では土木工事共通仕様書において、「施工計画書は着手前に提出」とあり、さらに、工事着手について「受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。」と定めているため、土木工事の受注経験のある工事業者さんはこの30日というのを一つの目安にされているケースもあります。