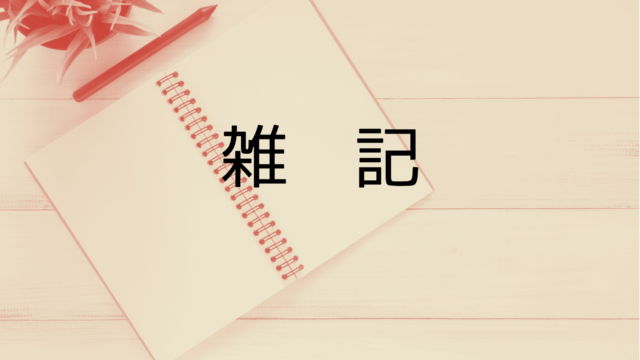消防庁の統計によると、昨年1年間に国内で発生した建物火災のうち、「電気」に関係する火災が12%近くを占めています。
件数で言えば2,400件以上で、「こんろ」に次いで2番目となっています。
電気による出火原因のひとつで、とくにこれからの季節に注意が必要なのが低圧進相コンデンサの発火事故。
進相コンデンサとは
交流で電流の位相が電圧より90°進むコンデンサの性質を利用し、モーターなどの遅れ力率を打ち消すために使用される機器
この内、200Vや400Vなどの低圧で使用されるものは、工場や店舗の分電盤などにも設置されています。
低圧進相コンデンサの発火原因は、経年劣化に伴う絶縁破壊です。
日本電機工業会によると低圧進相コンデンサの耐用年数は10年とされていますが、とくに1975年(昭和50年)以前に製造されたものは、故障時に電源から切り離す保安装置が内蔵されていないため、万が一の際には事故につながる危険性が高くなります。
コンデンサの発火事故が夏に多い理由は、機器本体の温度上昇が絶縁劣化を早めるからと言われています。
しかし、前回記事の受水槽と同じく、これにも予兆があります。
内部で絶縁破壊が進んだり、保安装置が動作するとケースが異常に膨れるため、定期的に点検をすることで事故を未然に防ぐことができます。(高圧コンデンサは受変電設備に含まれるため保全の分類では予防保全になりますが、低圧コンデンサは分電盤側に含まれることもあり、その場合は監視保全となります)
ちなみに、保安装置の内蔵や保安機構付きの使用については内線規程や公共建築工事標準仕様書でもJIS C4901「低圧進相コンデンサ(屋内用)」への適合として規定されています。
低圧進相コンデンサによる火災を防ぐためには
使用していない機器はブレーカーを切る
低圧コンデンサはモーターやポンプなどの機器ごとに取り付けられていることが多いですが、機器を使用していなくてもブレーカーがONだとコンデンサには電圧がかかっていますので人がいないときに発火する危険もあります。
1975年(昭和50年)以前に製造されたコンデンサは保安装置内蔵のコンデンサに交換する
1975年以降のものでも20年以上経過したものやケースに異常な膨らみが見られる場合は専門業者に点検を依頼してください。(製造年は本体銘板に記載)
また、高温多湿環境での使用は寿命を早めることになるので、内線規程でも「湿気の多い場所又は水気のある場所及び周囲温度が40℃を超える場所」などを避けて設置するよう規定されていますので注意が必要です。
出典:日本電機工業会